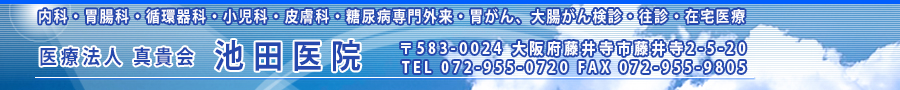| 図 1(症状) |
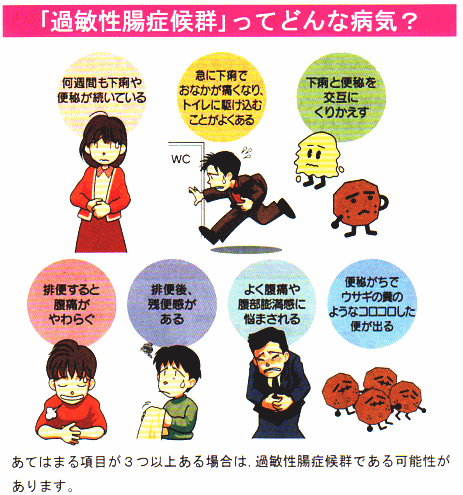 |
|
| 図 2(IBSとの共存が多い疾患 |
図 2(IBSとの共存が多い疾患)
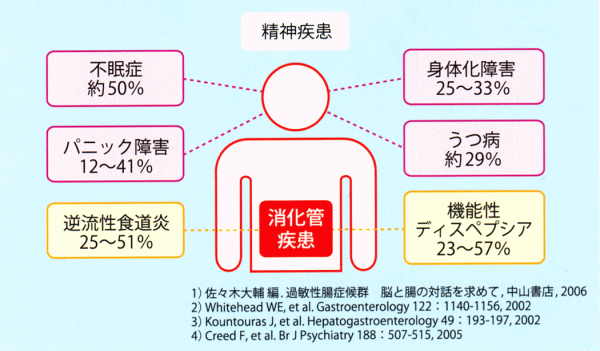 |
|
| 図 3(IBS診断、治療の流れ、アルゴリズム) |
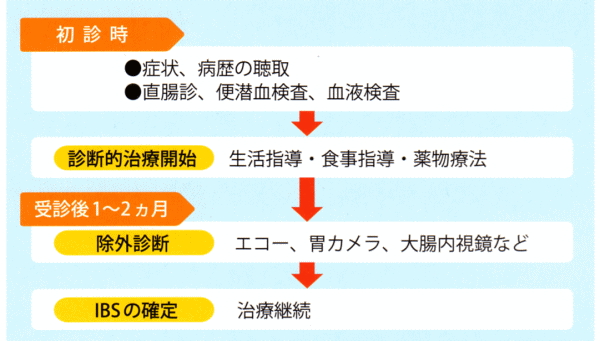 |
|
| 図 4(IBS問診時のポイント) |
図 4(IBS問診時のポイント)
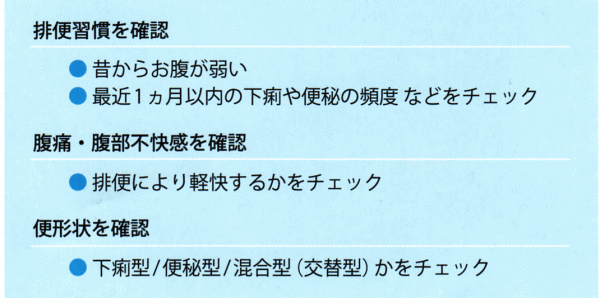 |
|
| ROMEⅢに基づいた過敏性腸症候群(IBS)の診断・治療のガイドライン |
| IBSに対して国際的な診断基準を統一しようという気運が高まり、2006年4月に国際的基準が改訂されたのがROMEⅢ基準です。以下参考として下記に示しました。 |
|
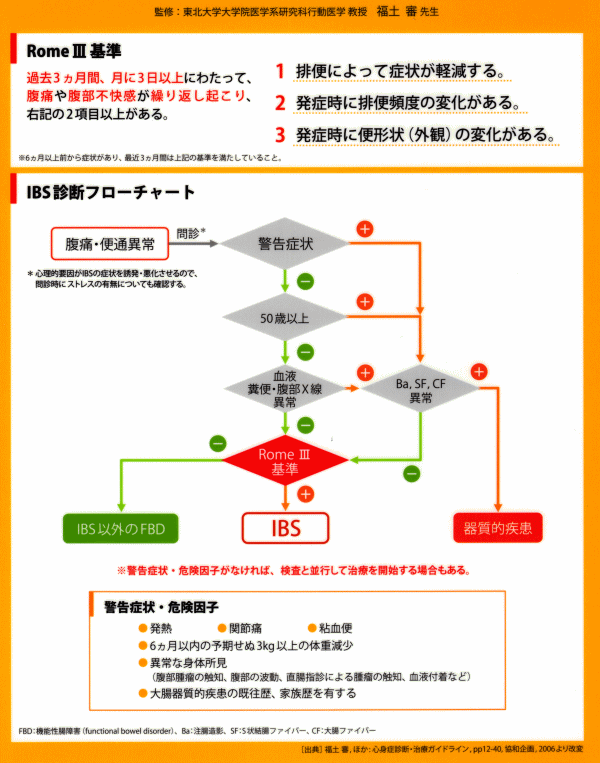 |
|
| 過敏性腸症候群(IBS)の治療 |
腸の機能を適切にコントロ-ルするには、腸管固有の運動機能、水分バランス、食事内容、食物繊維の摂取量、腸管内細菌のバランスが重要です。
便の組成をみると、普通便の水分含有量は約75%で、その水分量の5%の増減で軟便,硬便となり、便性状はわずかな水分量によって変化するため、便の水分バランスを調整することで良好な便通を得ることができるということがわかります。
また食物繊維は保水性を有し、便容量の増加、腸管内通過時間の短縮のほか、腸内圧を低下させる働きがあり、消化管運動にも密接にかかわっています。
しかし現代人の食物繊維摂取量は一日あたり約15g以下であり、健康的な生活を送るための20~25g/日を大きく下回っています。
このように食事内容の変化もIBS発症の大きな要因となっていると考えられています。
IBSの第一段階のガイドラインを下記に示しました。
高分子重合体は最近IBSの基本薬とされています。
この薬は水と一緒に飲むことで胃の中で食物と混ざり合い、腸の中で水分を吸収してふくらみ、ゼリ-状になって吸収した水を腸管内容物から逃さないようにする薬です。
便秘の患者さんでは、便の量を増やすとともに便をやわらかくして、ちょうどよい硬さの便がちょうどよい量でるようにします。
下痢の患者さんでは、水様~泥状の便を形のあるちょうどよい硬さの便にして、排便回数を減らします。
他にIBSに漢方薬が効果的な方もいらっしゃいます。
|
| 図6(患者さんの注意すべきこと) |
 |
| 図7(IBSの治療ガイドライン) |
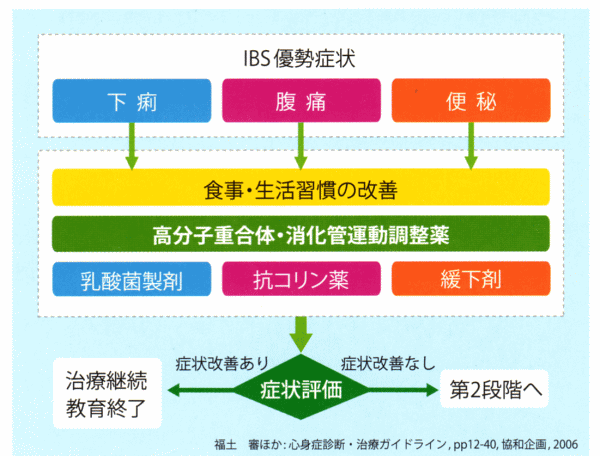 |